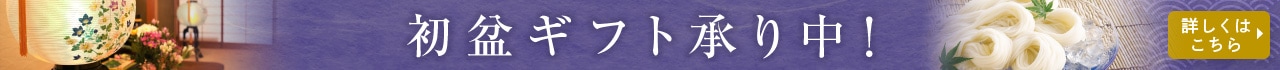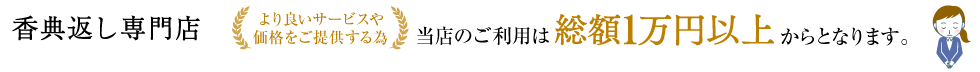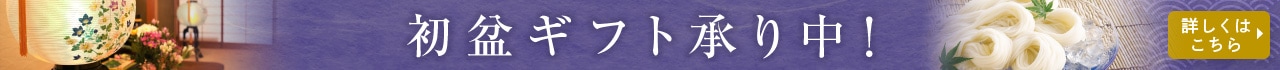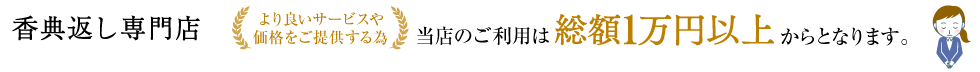§іј¬µо§Ђ§й49∆ь(їЌљљґе∆ь)§ё§«§ќ∆¶√ќЉ±
ЅтµЈЄе§ќ∞ІїҐ≤у§к§ §…°ҐЅтµЈЄе§ќќЃ§м§»…ђЌ„§ Љк¬≥§≠
ЅтµЈЄе§ќќЃ§м

ћµїц§Ћ§™ЅтЉ∞§тљ™§®§њ§Ґ§»§Ћ§в°ҐЅ”Љз§дЄж∞д¬≤§ќ э§Ћ§ѕ§д§л§ў§≠§≥§»§ђ§њ§ѓ§µ§у§Ґ§к§ё§є°£§є§ў§∆§ќЋ°Ќ„§т§ƒ§ƒ§ђ§ §ѓљ™§п§й§ї§л§њ§б°ҐЇ£≤у§ѕЅтµЈЄе§ќќЃ§м§дјґїї≈щ§ќЉк¬≥§≠§т§іЊ“≤р§Ј§ё§є°£§д§л§ў§≠§≥§»§тѕ≥§мћµ§ѓљ™§®§й§м§л§и§¶°ҐїцЅ∞§Ћ•Ѕ•І•√•ѓ•к•є•»§тЇојЃ§Ј≥иЌ—§є§л§≥§»§т§™§є§є§б§Ј§ё§є°£
ЅтЉ∞≈ц∆ь
°Џ1°џЉЂ¬р§ќЄеЊю§кЇ„√≈§Ћ∞дєь§т∞¬√÷§є§л ЄеЊю§кЇ„√≈§»§ѕ°Ґ≤–Ѕт§тљ™§®§њ∞дєь§»∞ћ«„§т∞¬√÷§є§лЇ„√≈§«§є°£∞м»ћ≈™§Ћ§ѕЊЃіщ§д»Ґ§т∆у√ §Ђї∞√ ј—§я°Ґ«т§§…џ§т»п§їЊЃЇ„√≈§тЇојЃ§Ј§ё§є°£ЄљЇя§«§ѕЅтµЈЉ“§ђјя√÷§Ј§∆§ѓ§м§лЊмєз§в§Ґ§л§и§¶§«§є°£ЄеЊю§кЇ„√≈§Ћ§ѕ∞дєь§»∞мљп§Ћ§™∞ћ«„°Ґјюєб°ҐЄж∞д±∆°Ґ§™≤÷°Ґґ° ™§т«џ√÷§Ј§ё§є°£
°Џ2°џ§™єб≈µ§ќј∞Ќэ §™єб≈µ§ќј∞Ќэ§ѕЅ«Ѕб§ѓљ™§®§л§и§¶§Ћ§Ј§ё§Ј§з§¶°£єб≈µ ÷§Ј§ќ§≥§»§вєЌќЄ§Ј§ƒ§ƒћЊ н§в§≠§Ѕ§у§»ј∞Ќэ§є§л…ђЌ„§ђ§Ґ§к§ё§є°£§іЋІћЊƒҐ§Ђ§й§™ћЊЅ∞§д§іљїљк§ђѕ≥§м§∆§§§њ§к°Ґ§™єб≈µƒҐ§»§™єб≈µ§ќґв≥џ§ђєз§п§ §Ђ§√§њ§к§є§лЊмєз§в§Ґ§к§ё§є§ќ§«°Ґ√н∞’њЉ§ѓ§™§≥§ §√§∆§ѓ§ј§µ§§°£
Ќв∆ь°Ѕ∞мљµі÷
°Џ1°џ∞ІїҐ≤у§к ∞ІїҐ≤у§к§ѕЅтµЈ§ќЌв∆ь§ЂЌв°є∆ь°Ґ√ў§ѓ§∆§вљйЉЈ∆ь§ё§«§Ћ§ѕЇ—§ё§ї§ё§є°£ЅтµЈ§«§™ј§ѕ√§Ћ§ §√§њґбљк§ќ э§дј§ѕ√ћт°ҐЉЂЉ£≤с°Ґїы±°°ҐЄќњЌ§ќґ–ћ≥ји§ §…§Ћ°Ґ≤ƒ«љ§ Є¬§кЅб§ѓї«§§§ё§Ј§з§¶°£±у≥÷√ѕ§Ћ§™љї§ё§§§«§Ґ§л§ §…§ќЌэЌ≥§Ђ§йЋђћд§ђЇ§∆с§ Њмєз§ѕ°Ґ§™≈≈ѕ√§д§™Љкїж§«§™ќй§тњљ§ЈЊе§≤§ё§є°£
єр ћЉ∞§ЋЌи§∆§§§њ§ј§§§њ≤сЅтЉ‘§ќ эЅі∞ч§Ћ∞ІїҐ≤у§к§т§є§л…ђЌ„§ѕ§Ґ§к§ё§ї§у§ђ°Ґ•ѕ•ђ•≠§д≈≈ѕ√§«§™ќй§тњљ§ЈЊе§≤§л§≥§»§ђ•ё• °Љ§«§є°£ƒЊј№§™≤с§§§Ј§њ§»§≠§Ћ°Ґ≤ю§б§∆іґЉ’§ќµ§їэ§Ѕ§т≈Ѕ§®§ё§Ј§з§¶°£
∞ІїҐ≤у§к§ѕЅ”Љз§»∞д¬≤∞мњЌ§ќ∆уњЌ§«≤у§к§ё§є°£ƒєµп§ї§ЇЅб§б§Ћ∞ъ§≠Ње§≤§л§≥§»§ђќйµЈ§«§є°£ƒћќг§»§Ј§∆…юЅх§ѕќђЅ”…ю§«§є§ђ°ҐЅтµЈ§Ђ§й∆у°Ґї∞∆ьЈ–≤б§Ј§∆§§§лЊмєз§ѕ√ѕћ£§ њ…ю§«§вєљ§§§ё§ї§у°£…ђЌ„§ј§»ї„§п§м§лЊмєз§ѕ°Ґ§™ќй§ќµ§їэ§Ѕ§»§Ј§∆≤џї“јё§к§ §…§тїэї≤§Ј§∆§ѓ§ј§µ§§°£
°Џ2°џЅтµЈЉ“§»…¬±°§Ў§ќјґїї ЅтµЈЉ“§Ў§ќјґїї§»ґ¶§Ћ°ҐЄќњЌ§ђ∆ю±°§Ј§∆§§§њ…¬±°§ќјґїї§вЋЇ§м§∆§ѕ§ §к§ё§ї§у°£ЅтµЈЉ“§Ў§ѕ≈ц∆ь§Ђ§й∞мљµі÷ƒш≈ў§ќЌЊЌµ§тїэ§√§∆їў І§¶Њмєз§ђ¬њ§§§и§¶§«§є°£•ѓ•м•Є•√•»•Ђ°Љ•…§«§ќїў І§§§дјЄћњ ЁЄ±ќЅ§ђїў І§п§м§∆§Ђ§й§ќјЇїї§тЉх§±…’§±§∆§§§лЅтµЈЉ“§в§Ґ§к§ё§є§ќ§«°ҐїцЅ∞§ЋЅтµЈЉ“§Ћ≥ќ«І§Ј§∆§™§ѓ§»ќ…§§§«§Ј§з§¶°£
°Џ3°џљйЉЈ∆ьЋ°Ќ„§ќља»ч љйЉЈ∆ь§»§ѕїаЄеЉЈ∆ьћ№§Ћє‘§¶Ћ°Ќ„§ќ§≥§»§«§є°£ЄќњЌ§ђї∞≈”§ќјо§Ћ√©§к√е§ѓ∆ь§ђїаЄеЉЈ∆ьћ№§»§µ§м°ҐЈгќЃ§«§ѕ§ §ѓіЋ§д§Ђ§ ќЃ§м§ќјо§т≈ѕ§л§≥§»§ђ§«§≠§л§и§¶§ЋµІ§к§тєю§б§∆є‘§§§ё§є°£Ї«ґб§ѕЅт≤»§ќ…й√і§тЄЇ§й§є§њ§б°Ґ§ё§њ°ҐЇ∆§”њ∆¬≤§ђ∞м∆≤§Ћ≤с§є§л§ќ§ђЇ§∆с§«§Ґ§л§њ§б§Ћ°ҐЅтµЈ≈ц∆ь§ЋљйЉЈ∆ьЋ°Ќ„§тЈЂ§кЊе§≤§∆±ƒ§а§≥§»§ђЅэ§®§∆§§§ё§є°£
°Џ4°џ∞д… §ќј∞Ќэ ∞д¬≤§»ЄќњЌ§ђ∆±µп§Ј§∆§§§њЊмєз§ќ∞д… ј∞Ќэ§ѕ§љ§м§џ§…Ї§∆с§«§ѕ§Ґ§к§ё§ї§у§ђ°ҐЄќњЌ§ђ∞д¬≤§»ќ•§м§∆љї§у§«§§§њЊмєз°Ґ∞д… §ќј∞Ќэ§Ћїюі÷§ђ§Ђ§Ђ§к§ё§є°£ƒ¬¬я§«§Ґ§м§–…ф≤∞§ќЈјћу≤тљь§д∞д… §ќЌєЅч°ҐЉЉ∆в§ќјґЅЁ§т§™§≥§ §¶…ђЌ„§ђ§Ґ§к§ё§є°£
§≥§ќ§»§≠∞дЄјљс§ќЌ≠ћµ§Ћ§ƒ§§§∆°Ґ…ђ§Ї≥ќ«І§Ј§∆§ѓ§ј§µ§§°£ЄќњЌ§ќ∞дї÷§т¬Їљ≈§Ј§ §ђ§й°Ґ∞дїЇ ђ≥д§дїаЄе§ќЉк¬≥§≠§тњ §б§л§њ§б§Ћ§в∞дЄјљс§ќЌ≠ћµ§ѕ§»§∆§вљ≈Ќ„§«§є°£
∞мљµі÷°ЅїЌљљґе∆ь
°Џ1°џ§™ ©√≈§ќЉк«џ ©√≈§т√÷§ѓЊмљк§»…ф≤∞§тЈи§б°Ґ§Ґ§лƒш≈ў§ќ•§•б°Љ•Є§тїэ§√§∆ ©√≈≈є§Ћє‘§ѓ§≥§»§т§™§є§є§б§Ј§ё§є°£§™ ©√≈§»ґ¶§Ћ∞ћ«„§дЋ№¬Ї§ §…§т∞мљп§Ћ¬Ј§®§л§≥§»§ђ∞м»ћ≈™§«§є°£ЉЂ ђ§ќ≤»§ќљ°«…§Ћ§и§к¬Ј§®§л§ў§≠ ©ґс§ђ —§п§л§њ§б°ҐїцЅ∞§Ћƒі§ў§∆§™§ѓ…ђЌ„§ђ§Ґ§к§ё§є°£
°Џ2°џ§™ и§ќЉк«џ §ё§Ї§ѕ∞дєь§т«Љ§б§лЊмљк§тЈи§б§ё§є°£§™ и§ђ§Ґ§лЊмєз§ѕ°ҐЈ—Њµ§є§л§њ§б§ќћЊµЅ —єє§тє‘§¶…ђЌ„§ђ§Ґ§к§ё§є°£§™ и§ђ§ §§Њмєз§ѕњЈ§њ§Ћќо±а§т√µ§Ј°Ґј–Їа≈є§ЎѕҐЌн§Ј§ё§Ј§з§¶°£± ¬еґ°Ќ№§тє‘§¶«Љєь∆≤°Ґїґєь§ §…§ќЉЂЅ≥Ѕт§»§§§¶Ѕ™¬тїи§в§Ґ§к§ё§є°£
°Џ3°џїЌљљґе∆ьЋ°Ќ„§ќ∆ьƒш§тЈи§б§л јµЉ∞§Ћ§ѕїЌљљґе∆ь§Ѕ§з§¶§…§Ћє‘§¶Ћ°Ќ„§«§є§ђ°ҐЄж∞д¬≤§ђљЄ§ё§к§д§є§§∆ьƒш§Ћ§є§л§≥§»§ђ¬њ§§§«§є°£ њ∆ь§ЋљЄ§ё§л§≥§»§ђ∆с§Ј§§Њмєз§ђ¬њ§§§њ§б°ҐЉ¬ЇЁ§Ћ§ѕїЌљљґе∆ьƒЊЅ∞§ќ≈Џ∆ь§Ћ±ƒ§ё§м§л§≥§»§ђ∞м»ћ≈™§«§є°£їЌљљґе∆ьЋ°Ќ„§ќЅ∞≈Ё§Ј§ѕ≤ƒ«љ§«§є§ђ°ҐїЌљљґе∆ь§т≤б§Ѓ§л§≥§»§ѕ»т§±§∆§ѓ§ј§µ§§°£§ё§њ°ҐїЌљљґе∆ьЋ°Ќ„§тї∞•цЈо§ЋѕЋ§√§∆§™§≥§ §¶°÷ї∞ЈоЄў°„§ѕЈ…±у§µ§м§л…чљђ§ђ§Ґ§к§ё§є°£∆ьƒш§тЈи§б§њЄе§ѕ°Ґ≤сЊм§ќЉк«џ°Ґї≤≤√Љ‘§Ў∞∆∆вЊх§ќЅч…’°Ґєб≈µ ÷§Ј§ќЉк«џ§тє‘§§§ё§Ј§з§¶°£
§™§п§к§Ћ
§™ЅтЉ∞° ƒћћл§Ђ§йєр ћЉ∞§Ћ§§§њ§л§ё§«°Ћ§ќќЃ§м§т§™§™§ё§Ђ§Ћ«ƒ∞Ѓ§Ј§њЄе°ҐЇў§Ђ§§є‘∆∞§т≥ќ«І§Ј°Ґ§љ§ќє‘∆∞§Ћ»Љ§¶•ё• °Љ§т√ќ§к§ё§Ј§з§¶°£…—»Ћ§Ћї»Ќ—§є§л√ќЉ±§«§ѕ§Ґ§к§ё§ї§у§ђ°Ґ∞м»ћЊпЉ±§»§Ј§∆јµ§Ј§§•ё• °Љ§»ќЃ§м§т«ƒ∞Ѓ§Ј§∆§™§≠§ё§Ј§з§¶°£
Ґ®ЅтЇ„§Ћ§ё§ƒ§п§лї≈Ќи§к§д•ё• °Љ§Ћ§ѕЌЌ°є§ єЌ§® э§д√ѕ∞и§ќ∆√ј≠§ђ§Ґ§к°Ґ
°°§≥§Ѕ§й§«Њ“≤р§Ј§∆§§§лєаћ№§ђ…ђ§Їјµ§Ј§§§»§§§¶§в§ќ§«§ѕ§і§ґ§§§ё§ї§у§ќ§«§і√н∞’§ѓ§ј§µ§§°£
49∆ь(їЌљљґе∆ь)§ќєб≈µ ÷§Ј§ќ§іЅк√ћ§ §й•Ѓ•’•»•Є•г•—•у§Ў°™Ї«√їЌв∆ь§ЋїсќЅ§т§™∆ѕ§±√„§Ј§ё§є°£
іЎѕҐµ≠їц
•Џ°Љ•ЄTOP